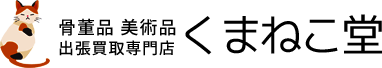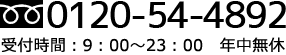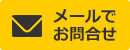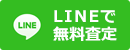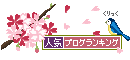買取事例
遺品買取 遺品整理 生前整理 中野区
東京都中野区の遺品買取 遺品整理 生前整理をお考えの方へ くまねこ堂では故人のご愛用の古い品物やコレクションも適正価格で買取ます。 東京都中野区で「遺品整理」「遺品買取」「生前整理」をするなら「遺品整理業 くまねこ堂」へ。くまねこ堂では、中野区のすべての遺品を買い取れるわけではあ ...
遺品買取 遺品整理 生前整理 豊島区
東京都豊島区の遺品整理 遺品買取 生前整理をお考えの方へ くまねこ堂は故人がご愛用していた古い物や収蔵品を適正価格にて買取ります。 東京都豊島区で「遺品整理」「遺品買取」「生前整理」をするなら「遺品整理業 くまねこ堂」へ。くまねこ堂では、豊島区のすべての遺品を買い取れるわけではあ ...
遺品買取 遺品整理 生前整理 調布市
東京都調布市の遺品整理 遺品買取 生前整理をお考えの方へ くまねこ堂が故人様が愛用していた古い品や収集品を適正価格で買取致します。 東京都調布市で「遺品整理」「遺品買取」「生前整理」をするなら、ぜひくまねこ堂の遺品整理業まで。くまねこ堂では、調布市のすべての遺品を買い取れるわけで ...
遺品買取 遺品整理 生前整理 台東区
東京都台東区の遺品整理 生前整理 遺品買取をお考えの方へ くまねこ堂が故人様が愛用していた古い品や収集品を適正価格で買取致します。 東京都台東区で「遺品整理」「遺品買取」「生前整理」をするなら「遺品整理業 くまねこ堂」へ。くまねこ堂では、台東区のすべての遺品を買い取れるわけではあ ...
遺品買取 遺品整理 生前整理 墨田区
東京都墨田区の遺品整理 遺品買取 生前整理をお考えの方へ くまねこ堂は故人がご愛用していた古い物や収蔵品を適正価格にて買取ります。 東京都墨田区で「遺品整理」「遺品買取」「生前整理」をするなら、くまねこ堂の遺品整理業まで。くまねこ堂では、墨田区にございます遺品を全て買い取れるわけ ...
遺品買取 遺品整理 生前整理 江東区
東京都江東区の遺品整理 遺品買取 生前整理をお考えの方へ くまねこ堂が故人様が愛用していた古い品や収集品を適正価格で買取致します。 東京都江東区で「遺品整理」「遺品買取」「生前整理」をするなら、ぜひくまねこ堂の遺品整理業まで。くまねこ堂では、江東区のすべての遺品を買い取れるわけで ...
遺品買取 遺品整理 生前整理 板橋区
東京都板橋区の遺品整理 生前整理 遺品買取をお考えの方へ くまねこ堂では故人のご愛用の古い品物やコレクションも適正価格で買取ます。 東京都板橋区で「遺品整理」「遺品買取」「生前整理」をするなら、くまねこ堂の遺品整理業まで。くまねこ堂では、板橋区にございます遺品を全て買い取れるわけ ...
見本本「襲ね色目(かさねのいろめ)」のご紹介
いつもご利用ありがとうございます。リピーターのお客様から掛軸、書道道具、万年筆、カメラ、アクセサリー、レコード、CD、切手などをお譲りいただきました@東京都昭島市あさひ町
****************
3度目のリピーターのお客様のお宅へ即日出張をさせていただきました。
誠にありがとうございます!
襲ね色目(かさねのいろめ)という色見本をお譲りいただきました。
色目とは、日本の伝統的な色彩の組み合わせ表現で
有名な十二単(じゅうにひとえ)、これは言葉のまま十二枚の着物を着る女性の正装着なのですが
これもその辺にある着物を十二枚着ればいいというわけではなく、季節や風物に沿った色合いの着物を十二枚着なければいけません。
とはいえ、色の組み合わせなど考えれば無限大になってしまいます。
その時に使うコーディネート帖がお譲りいただいた「襲ねの色目」です。
十二単は今でいうスーツレベルのガッツリ正装ですが
たいていの装束は2枚か3枚ぐらいを重ねるのが普通です。
日本の伝統色の名前には日本で見られる四季の植物や花、鳥や動物の色に由来する日本独特の色名が使われていますが、そんな風にすべてのものから色を抽出したらキリがないのでは…
と思われるかもしれませんが本当にその通りで、その数は「1000種類」を超えていると言われています。
昔、というとどうしても茶色っぽいというか草木で染めたような地味な色合いをイメージしがちですが
実は現代よりもずっとカラフルで派手だったんじゃないかなーと個人的には思います
当時の絹は非常に薄く、裏地の色が透けるため、透けて見える独特の色合いを楽しんだといわれています。
非常にやんごとない感覚です。
着物に限らず、和菓子などもそうですが
江戸時代という昔から「透ける」というものに美しさや上品さを見出していた日本人の繊細な感性はいつでもなくならないでほしいところだなあ、と思います。 ![]()
ヨシダ
スタッフの買取同行記~出張買取の様子~
街中の木々の蕾がふっくらして参りましたね。
春休みに突入したこの時期!もうお引っ越しラッシュが始まっております~ !
!
昨日訪問させていただいたお客様も、お引っ越しの際のご整理でした。
出張買取のご依頼、誠にありがとうございます!
ご対面早々、お客様「ここに電話で話した石があるんですよ~!」と駐車場のシャッターを開けてくださいました!
ありがとうございます!
駐車スペースの中に早速お譲りいただけるお品物が
立派な石です!おふたつもお譲りいただき、ありがとうございます!
さてさてお次はそのままお家にお邪魔させていただき、(ここで玄関にてお客様の奥様方にご挨拶!こんにちは!よろしくお願い致します~!)
 畳のお部屋へGO!
畳のお部屋へGO!
そこで店主くまきちとスタッフを待ち受けていたのは、木彫りの置き物やお茶道具、陶磁器等々、、、。
沢山のお品物を畳に並べてくださっておりました!ご家族総出でお引っ越しの支度の最中、ありがとうございます!
畳のお部屋のお品物を拝見させていただいた後は~
階段を上がった所にあるお部屋にGO!
掛軸、花瓶、碁盤、碁石、将棋の駒等を!
階段を上がった所にあるお部屋の次は~
応接室のようなお部屋にGO!
本や細かなアクセサリー類、絵画、版画等を!
応接室のようなお部屋のお次は~
ダイニングやキッチンにGO!
洋食器やガラスのコップ、切手やコイン等等、、、!
お客様とご一緒に、ぞろぞろツアーの如く、お家を一周させていただきました。(ご案内ありがとうございます!)
 ここでキティちゃんのメモをピックさせていただいた時のやり取りをひとつご紹介させていただきます。
ここでキティちゃんのメモをピックさせていただいた時のやり取りをひとつご紹介させていただきます。
お客様「え~!キティちゃんまで持ってってくれるの!?本当に何に価値があるかわからないねえ![]() 」
」
店主「そうですよ~だから全部捨ててしまう前にお呼び頂けてこちらも嬉しいです、ありがとうございます~ !」
!」
そうです!お客様がお値段がつくかも!?と期待を寄せられるお品物よりも、もうゴミだからあとは捨てるだけ!と思ってゴミ袋に入れる寸前だったお品物の方がお値段が付いたりすることもあります。
自分ではゴミだと思っているモノの処分をご検討中のお品物があるお方!(特に奥様方!)是非一度ご相談くださいませ!
 お家をぐるっと一周させていただいた時には、各お部屋にお譲りいただく予定のお品物で出来たお山がお部屋ごとに出現しておりました
お家をぐるっと一周させていただいた時には、各お部屋にお譲りいただく予定のお品物で出来たお山がお部屋ごとに出現しておりました![]()
そしてそのお部屋ごとに出現したお山を、お客様立会の元、店主くまきちが査定してゆきます!
査定、精算が終了し、お譲りいただいたお品物を車に積ませていただいて、今回も無事に終了いたしました。
お忙しい中、お家の中をグルりとお邪魔させていただき、また、たくさんのお品物をお譲りいただき本当にありがとうございました

かこさん
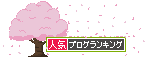
人気ブログランキング
唯一無二のプレミアムなコニャック REMY MARTINの「ルイ13世」のご紹介です。
コニャックでルイ13世といえば、口にしたことはなくても名前は聞いたことがある人は多いんじゃないでしょうか(私ですが!)
そもそもブランデーとはなんなのか?
ブランデーは、原料は果実(主にブドウ)で、ワインに醸造。さらに、それを蒸留したものが「ブランデー」となります。
ちなみに、よく似ているウイスキー。
ウイスキーの主な原料は麦などの穀物のため、ビールを蒸留すると「ウイスキー」になります。
見た目はよく似てても全然違うんです
ルイ13世が生まれたのは1874年。
実は中身のコニャックよりデキャンタが先に誕生し、最高のデキャンタに詰める酒はさて何がいいか。
やっぱり家族や身内だけにふるまわれる「ファミリーリザーブ」こそふさわしい!として詰められてできあがったのがルイ13世です。
ファミリーリザーブは生産者のパーソナル性のあるものだとして、コニャックという枠組みでは最高位なんだそうです。
コニャックはブレンディングが命といわれていることからも、コニャックは様々な原酒の掛け合わせとなっております。
ちなみにルイ13世はそのブレンドされている原酒数がなんと「1200種」![]()
また、ルイ13世はいつの時代もルイ13世でいなければならない。ということから、誕生した143年前から今手に入るクオリティは全く変わっていないそうです。
よくパン屋さんやうどんやさんが「食べ物は生き物だからその時の材料の状態や気温や湿度によって配合を変えてる」みたいなのありますが
ギルティ!ってことですね…
味に関しては100種類にも及ぶ味を感じられるらしく
ルイ13世のセラーマスター曰く、最初に鼻腔にひろがるのはフローラル、たとえばジャスミン、ユリのよのうな白い花の香り。
次に洋梨、ピーチ、イチジクといったフルーツの香り。
空気と交わっていくことでキャラメル、バニラ、カカオ、そしてターメリック、ピンクペッパーなどスパイシーさもある。
ということですが、正直舐めたこともない私からすると、マジか…ってぐらい複雑そうです。
唯一無二という名は伊達ではないという事ですね…..
お酒というよりはアートのように感じます。
ヨシダ